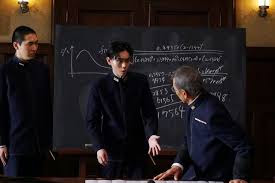2019年に話題になった、台湾プロ野球のチアリーダーが、再びブームになっているらしい。先日、僕のスマホにもYouTubeからおすすめ動画が送られてきた。断っておくが、僕は普段から若い女の子の動画ばかりを見ているわけではないので、YouTubeのアルゴリズムが、なぜ台湾チアの動画を送りつけてきたのかは不明である。
トランペット隊は、動画によって、生演奏の時と録音アンプの時がある。生演奏の時のトランペット隊は、バックネット裏の上の方にいるようだ。で、日本との大きな違いは、内野席の一塁側にも三塁側にもホームの応援団がいることだろう。だから、チアリーダーたちも両側のダグアウト上にいる。一方、ビジターの応援団は外野席という雑な扱いだから、アウェーの疎外感は此の上なく大きい。まあ、日本がビジタ-に優しすぎるんだろうけど。
チアは攻撃の時にダンスをして、守備の時は基本的に休憩。試合の前半と後半で場所を入れ替えるので、一塁側三塁側のどちらに座っても、差が無いようになっているらしい。彼女たちはビジターの試合には同行しないそうだから、「峮峮」に会いたければ、中信兄弟の本拠地「台中洲際棒球場」に行くしかないということになる。
チュンチュンは大学院卒で経営学の修士号をもつ、いわゆる高学歴タレントである。学生時代からタレント活動をしていたそうだが、大学院の進学時には、1年間活動を休止していたとあった。チアリーダーのオーディションを受けたのは、大学院卒業後の2016年だから、遅いスタートと云える。当時は、ダンスの経験も無く、野球のルールも知らなかったそうだ。2017年ころの動画がアップされているが、確かに、可愛いけれど、ダンスは上手とは云い難い。彼女が日本でバズったのは2019年で、そのころの動画が質的にも量的にも充実しているように思う。
チュンチュンは、チアとしては小柄である。彼女の魅力は、その小さな体をフルに使って踊るところにある。チアダンスは、誰でも真似できるような単純な動きの繰り返しだ。高いダンススキルは必要ないかわりに、魅せるのは難しい。あの振り付けで人を惹き付けられるのが、彼女の凄いところ。彼女の称号は「可愛すぎるチアリーダー」だが、それは「ダンスする姿が」という意味である。
僕は、「元気をもらう」という表現が、あまり好きでなかったけれど、チュンチュンには、この言葉が似合うし、この言葉しか思いつかない。チアリーダーの仕事は、応援すること。彼女の動画を見て、ヲタクが元気づけられるのは、彼女が天性のチアリーダーだからである。
実は、彼女は2年前に悲しい経験をしている。このことがなければ、つまり彼女が可愛いだけのチアリーダーであったなら、僕はこの記事を書くことはなかっただろう。
彼女は、2020年の6月に、台湾の人気タレント「小鬼」こと「黄鴻升」さんとの熱愛を報道された。小鬼さんがチュンチュンのマンションに14時間滞在していたというものだ。両方の事務所が「お友達宣言」を出したものの、彼女たちの仲は公然の秘密だったらしい。チュンチュンも当時30歳、結婚引退説も出ていたそうだ。
ところが、黄鴻升さんは、報道の3ヶ月後に自宅の浴室で転倒し亡くなってしまう。司法解剖の結果は、転倒したことによる急性心筋梗塞。その日の深夜、彼女はインスタグラムを更新し、彼に対する想いを綴った。
当然のことであるが、原文は中国語である。ネットにはいくつかの日本語訳が投稿されているので、引用させていただこう。
毎日 どうしてこんなに幸せなんだろうと思っていた。
毎日 どうしてこんなに合う人に巡り会えたのだろうと思っていた。
毎日 あなたに出会えたことを天に感謝していた。
2人の時はいつも家で過ごしていたけど退屈でもなく、喧嘩もしないで楽しかった。それでもバレてしまったけど。あなたは私たちの関係を公表しない方がいいと思っていた。だから私たちは「良い友達」だった。
でも、私には、もうどうしようもなく辛すぎる。メディアやネット民がなんて書くか、気にしないなんて私にはできない。もう装うことはしたくない。ごめんなさい。約束を破ってしまって。
これまでずっと私を守ってくれて、可愛がってくれてありがとう。私がどんな要求をしても、無理難題でもあなたはしてくれた。どこに行っても、何をしていても、誰が居ても、いつも私に写真や動画を送ってくれた。仕事以外、シャワーを浴びてても寝ていても、いつも「秒」で返事をくれた。私を安心させるために。この一年半近くの間。ずっとそうだった。
でも昨夜、私はどうしてもあなたと連絡が取れなかった。これまではいつもあなたが私のところに来てくれた。携帯以外、私にはあなたと連絡を取る手段がなかった。自分が本当に無力だったことに気づいた。
二週間前、あなたは突然「僕たち、結婚しなくてもいいよね?」と言った。「どうして?」「結婚しなければ、この先何があっても君に迷惑は掛からない。君は白紙の状態で誰かと結婚できる。」と。
でも、黄鴻升 私はあなただけが必要だった…
人生 真的太難太難了…(人生って本当に難しい)
どうやら二人の交際は、小鬼さんがチュンチュンのマンションを訪ねるかたちで行われていて、チュンチュンは小鬼さんの自宅へ行くことはなかったようである。小鬼さんは、翌朝、彼を心配して訪ねてきた父親によって発見されている。
36歳という若さでの突然死ということ、直前に彼女に意味深長なことを話していたことなどから、自殺説も飛び交ったらしい。コロナ禍で、日本でも多くのタレントさんが将来の不安から自ら命を断っていた時期であるから、そのような噂が出てくるもの無理はないと思う。
彼女が、彼との約束を破って、交際を公表したことについては、「売名行為」という批判も受けたらしい。これに対してブチ切れたチュンチュンのコメントが、ネットに紹介されている。
誰も好き勝手に他人を批判すべきじゃない。あなたたちは私たちが歩んだ道を歩いたことはないし、私たちの生活も経験していない。もし、私のことを売名と思うなら、これ以上私にはつきまとわないで欲しい。
みんなそれぞれの考え方がある。言論の自由は、人を傷つけていいという意味ではない。
さらに、チュンチュンは、交際を明かした理由を「彼の最後を全部見送りたかったから」と説明した。
彼女は、3日間にわたって行われた「お別れの会」にすべて出席し、火葬、納骨にも「黄鴻升」さんの家族らと共に参列したらしい。納骨などは、日本でも台湾でも肉親だけで行うことだろうから、彼と彼女が公認の仲であったことが分かる。
確かに、「良い友達」が納骨にまで参列していたら、「何で?」ってなる。彼女は堂々と参列して、ちゃんとケジメをつけたかったのだろう。
台湾のプロ野球もコロナ禍で無観客試合になったりして大変だったようだ。先週末には、3年振りにオールスターゲームが開催されたらしい。動画には、ちょびっとしか観客がいない球場が写っていることがあるが、コロナによる入場制限下のことであり、決して台湾プロ野球の人気が無いわけではないとのことである。念のため。